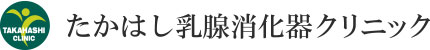妊娠後の授乳期乳がんについて
授乳期とは、出産から1年未満とするものと2年未満とするものがあります。
授乳期の乳がんは、若年者が多く、この若年齢層での全乳癌に対しての発生頻度は約3%であります。 妊娠期と授乳期の乳がんを合わせた場合、全年齢層での全乳癌に対する発生頻度は約0.8%です。
授乳期乳がんは、がんの悪性度が高く、非妊娠期や妊娠期乳がんよりも進行しやすく、リンパ節転移が多くみられために化学療法(抗がん剤治療)を受ける割合が高くなります。 再発や乳がん死亡が多いと言われています。 稀な病気ではありますが、今後、高齢出産および乳癌罹患率の上昇に伴い増加することが推測されています。
しかし、早期発見された場合には、予後は有意に良くなることがわかっています。
授乳期に発見された乳房腫瘤の多くは、授乳に伴う生理的変化,乳汁のうっ滞であるため経過観察となりやすい。 ところが乳房腫瘤が乳がんによる場合であっても、授乳期乳がんの頻度が少ないこともあり生理的変化の腫瘤とされやすい。 このことが授乳期乳癌の発見・診断時期を遅らせている原因の一つでもあります。
また、授乳期の乳房は、マンモグラフィで乳腺全体が高濃度を呈しやすく、乳がんがあっても写りにくく診断されにくい。
しかしながら授乳期という特殊な時期であっても、早期発見ができて適切な治療を受ければ、治癒する可能性は高くなります。 いつもと比べて胸の形、乳首の状態、乳房の張り感などが違う、授乳が終わった後なのに乳房に硬いしこりが残る、母乳に血が混じる、赤ちゃんが急に母乳を飲まなくなったなどの症状は、乳がんの発見につながる重要な兆候となりきっかけになります。
予後
授乳期乳がんの予後が悪いのは、乳がんの悪性度が高いだけでなく既に進行した乳がんの状態で発見されるためであります。 予後改善のためには、いかに妊娠前の普段から乳がん検診を受けるのが大切かつ大変重要であります。