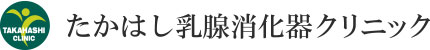妊娠期乳がんの薬物治療について
2021年5月26日
2025年2月18日
妊娠前期での薬物療法による先天性奇形の可能性は極めて高く、妊娠中後期ではその危険性が低くなるとされています。 しかし、化学療法(抗がん剤治療)による胎児発育不良や早産の割合が増加し、出産後の器官未成熟による合併症の増加も報告されています。
妊娠前期での抗がん剤治療は禁忌と考えられ、避けなければなりません。
妊娠中後期では抗がん剤により先天奇形の割合は大きく増加しないものの、胎児発育不良や早産の割合が増加する可能性があり、安全性が十分には確立されていません。
妊娠後期は、数週間であれば出産まで投与開始を遅らせる方法や、場合によっては帝王切開で早期に出産を行った後に抗がん剤治療を行うという選択肢はあり得ます。
ただし、抗がん剤治療は妊娠中期以降であれば胎児に影響も少なく投与できることが示されていますが、妊娠35週以降は分娩期の副作用(骨髄抑制など)を考慮して抗がん剤治療を行わないことが推奨されています。 よって抗がん剤を投与する場合には、最終投与から出産までの間隔は、新生児が骨髄抑制からくる好中球減少を伴って出生しないように、2週以上空けることが望ましい。
また、出産後には薬物の代謝が胎盤から新生児の肝・腎へと切り替わるので、新生児の臓器機能にダメ-ジを与えるおそれがあり、出産間際の抗がん剤投与は避けるべきであります。
一方で抗HER2療法やホルモン療法は胎児発育や子宮内環境への影響、胎児奇形を誘発する可能性などがあり、妊娠週数に関わらず行うべきではありません。
予後
妊娠期乳癌の予後が悪いのは、妊娠期乳がんが既に進行した乳がんの状態で発見されるためであります。 予後改善のためには、いかに妊娠前の普段から乳がん検診を受けるのが大切かつ大変重要であります。